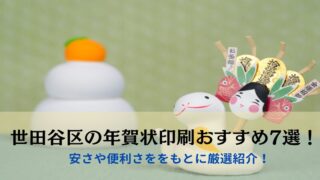 年賀状印刷
年賀状印刷 世田谷区の年賀状印刷おすすめ7選!安さや便利さををもとに厳選紹介!
世田谷区で年賀状印刷を探している方必見!安さと便利さを重視したおすすめ7選を厳選紹介。オンラインサービスや即日対応可能な店舗、身近なコンビニまで網羅!忙しい方や迷っている方はぜひこの記事を参考にして下さいね。
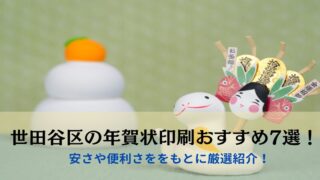 年賀状印刷
年賀状印刷  年賀状印刷
年賀状印刷 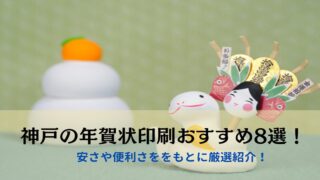 年賀状印刷
年賀状印刷 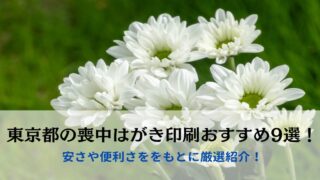 喪中ハガキ印刷
喪中ハガキ印刷 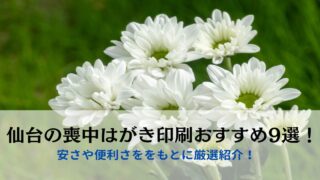 喪中ハガキ印刷
喪中ハガキ印刷 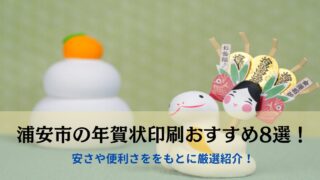 年賀状印刷
年賀状印刷 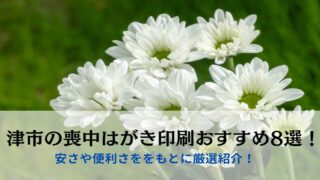 喪中ハガキ印刷
喪中ハガキ印刷 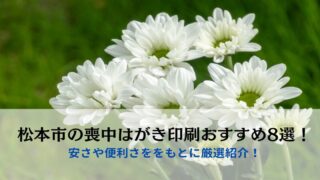 喪中ハガキ印刷
喪中ハガキ印刷 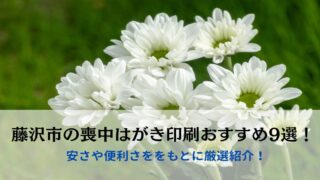 喪中ハガキ印刷
喪中ハガキ印刷 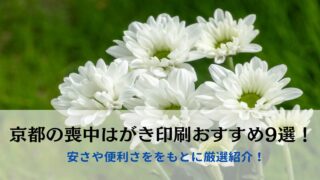 喪中ハガキ印刷
喪中ハガキ印刷